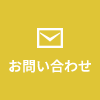企業はどう対応?2026年の下請法改正
令和7年5月16日に「下請代金支払遅延等防止法(現行の下請法:昭和31年制定)及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立し、施行日は令和8年1月1日とされています(一部の規定は改正法の公布の日から施行)。下請法は、委託事業者と委託先である受託(下請)事業者の間に生じる取引上の力関係の不均衡正し(取引の公正化)、立場の弱い事業者の利益を保護すること(下請事業者の利益保護)を目的として制定されており、今回の改正に伴い企業は様々な対応を求められることとなります。本記事では現行の下請法に関する法改正の概要と、企業としての注意点を解説します。
Contents
第1 改正の概要・趣旨
1 改正の概要・名称変更
現行の下請法は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)と改称され、適用対象となる事業者の拡大等を内容として改正されます。
今回の改正点は、以下のように整理できます。
- 用語の見直し
- 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
- 手形払等の禁止
- 対象取引について運送委託の追加
- 適用事業者に関する従業員基準の追加
- 面的執行の強化
- その他
第2以降で詳しく説明します。
2 改正の趣旨
近年の急激なコスト上昇を受け、これを適切に価格に転嫁させることによって、各事業者が賃上げを実現しつつ、持続的な経営を図っていくことが求められます。もっとも、従前の商慣習として、委託事業者が受託事業者に対して、価格決定や支払期日等に関し、負担を押し付けてた実情がありました。こうした商慣習を是正し、取引を適正化し、適切な価格転嫁を図っていくことを目的として取適法に改正されました。
第2 個別の改正点
1 用語の見直し
「下請」という用語が、発注者と受注者が対等な関係ではないとの語感があり、発注者(大企業)の側でも「下請」という言葉を使わなくなってきていることから、以下のように改正されました。
「親事業者」を「委託事業者」、「下請事業者」を「中小受託事業者」、「下請代金」を「製造委託等代金」に変更されます(取適法2条8項、9項)。
2 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
下請法では、親事業者の禁止行為として、下請事業者の給付の内容と同種または類似の給付に対し、通常支払われる対価に比し、著しく低い下請代金の額を不当に定めること(いわゆる買いたたき『下請法4条5号』。)及び、下請事業者に帰責事由がない場合の減額(下請法4条3号)が挙げられていました。
これに加えて、今回の改正により、「費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が」製造委託等代金額「に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じ」ない、または、協議において、「中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に」代金額を決定することが禁止されます(取適法5条2項4号)。
つまり、従前は、市場価格より著しく安価に価格決定をすること及び代金額の減額が禁じられていましたが、改正法により、コスト上昇に応じて代金額を上昇させる場面で、一方的に委託事業者が、代金額を据え置いたり、その上げ幅を低く決定したりすることも禁じられました。これにより、中小受託事業者の利益確保を促すことが期待されます。
3 手形払等の禁止
下請法では、代金の支払期日は、製品や役務を親事業者が受領した日から60日以内とされていました(下請法2条の2)が、手形による支払いは禁止されておらず、手形を使用した場合、手形の現金化に必要な期間についての資金繰りが中小受託事業者の負担となっていました。
そこで、手形払は禁止されることになりました。また、支払期日までに代金額に相当する額の金銭と引き換えることが困難なもの(電子記録債権(でんさい)、ファクタリング等)による支払いが禁止されました(取適法5条1項2号括弧書き)。
これにより、委託事業者が製品、役務を受領してから60日以内に中小受託事業者が代金を受領することができます。
4 対象取引について運送委託の追加
下請法では、(発)荷主から(元請)運送事業者への最初の運送委託については、「役務提供委託」(下請法2条4項)に該当しないため、(独占禁止法の物流特殊指定による対応という建付け)下請法の適用はなく、運送事業者が運送業務を他の事業者に再委託する場合のみが規制されていました。
荷主に対して立場の弱い物流事業者が、荷役や荷待ちを無償で行わされているなどの問題が、荷主・物流事業者間で発生していました。
そこで、この問題を解消し、機動的に対応するため、(発)荷主が(元請)運送事業者に対して物品の運送を委託する取引は「特定運送委託」(取適法2条5項)とされ、新たに規制対象となりました。
5 適用事業者に関する基準の追加
下請法では、親事業者に該当するかは、一定の資本金を超える事業者が、基準より低い資本金の事業者(個人を含みます。)に業務を委託しているかで判断され、資本金のみが基準とされていました(下請法2条7項、8項)。具体的な基準は以下の表の通りです。
| 業務内容 | 親事業者資本金 | 下請事業者資本金 |
|---|---|---|
| 製造委託等 | 3億円超 | 3億円以下 |
| 同上 | 1000万円超~3億円 | 1000万円以下 |
| 情報成果物作成委託または役務提供委託※ | 5000万円超 | 5000万円以下 |
| 同上 | 1000万円超~5000万円 | 1000万円以下 |
※プログラムの作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理については、情報成果物作成委託、役務提供委託に該当しますが、製造委託等の基準が適用されます(下請法施行令1条)。
これにより、実質的には、事業規模は大きいにもかかわらず、当初に投下した資本金が少額なままの事業者や、減資をすることで、下請法の適用を免れる事業者、及び、受注者へ増資を求める事業者が存在しました。
本改正により、事業規模を反映させる指標として、従業員数を用い、常時使用する従業員の数が一定数を超える事業者が、常時使用する従業員の数が一定数を下回る事業者に対して委託した場合も取適法が適用されるという基準が追加されました(取適法2条8項5号、6号、9項5号、6号)。
改正後は、資本金による基準または従業員数(300人)による基準いずれかを満たせば、取適法の適用対象です。従業員数の具体的な基準は、以下の表の通りです。
| 業務内容 | 委託事業者従業員数 | 中小受託事業者従業員数 |
|---|---|---|
| 製造委託等 | 300人超 | 300人以下(個人含む) |
| 情報成果物作成委託または役務提供委託(※は資本金基準と同じ) | 100人超 | 100人以下(個人含む) |
6 面的執行の強化
下請法では、事業所管庁には調査権限のみが与えられ、こちらに通報することを理由とした「報復措置」(取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。)は禁じられていませんでした(下請法9条3項、7条及び4条7号参照)。そのため、事業所管庁、公正取引委員会及び中小企業庁間で連携して、下請法を遵守させる体制の構築が必要でした。
取適法では、事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限が付与され(取適法8条)、こちらに対して通報したことを理由とする「報復措置」も禁じられることになりました(取適法5条1項7号)。また、「報復措置の禁止」の申告先として公正取引委員会及び中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣が追加されました。
7 その他の改正点
- 専ら製品の製造に用いる木型、治具、その他の物品の成形用の型、工作物保持具その他の特殊な工具についても、金型と同様に製造委託の対象物となりました(取適法2条1項)。
- 下請法においても、親事業者は、給付の内容、代金額、支払期日、支払方法その他の事項を書面または電磁的方法により、下請事業者に明示する義務を負っていましたが、このうち電磁的方法によるには、下請事業者の事前の承諾が必要でした(下請法3条2項)が、取適法においては、中小受託事業者による承諾は不要です(取適法4条参照)。
- 遅延利息の対象に、中小受託事業者に帰責性のない減額を追加し、起算日から60日を経過した日から実際に支払いをする日までの期間について、遅延利息の支払いが必要となりました(取適法6条2項)。
- 勧告時点において、委託事業者の取適法違反行為が是正されたとしても、禁止行為が排除されたことを確保するために必要な措置(再発防止策等)をとるべきことを勧告できるようになりました(取適法10条2項)。
第3 終わりに
今回の取適法への改正により、適用対象が広がり、禁止行為も増えることになりました。これまでの下請法による規制を前提として商取引を行うと、気づかぬ間に取適法違反になっているという状況が十分に生じ得る内容ですので、各企業の担当部署、担当者は注意が必要です。反対に、中小受託事業者側としては、これまでの商慣習により不利な取引を強いられていた点が、取適法により違法となり、是正される可能性も生じましたので、改めて取引先との契約書、取引の実態を確認することが健全な利益確保の点で重要です。
特に、従業員数基準、手形払等の禁止、運送委託に対する適用対象の拡大といった改正点は、旧来の取引先との関係にも影響を与える可能性が十分にあり、新たな取引先だけでなく、旧来の取引先との関係でも注意して、契約関係や取引先の状況を確認する必要があります。
取適法の適用対象になる取引を行っているか分からない、取適法対象事業者との間で代金額の決定方法をどうすべきかわからない等のお悩みがありましたら、弁護士に相談してみることをおすすめします。