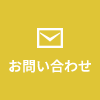公益通報者保護法改正について

企業の不正を是正するうえで重要な役割を果たす「公益通報者保護法」が、令和7年6月に改正されました。改正の背景には、通報制度の形骸化や、通報者が不当な扱いを受けるなどの問題意識があります。本改正により、企業の対応体制整備の義務が強化され、フリーランスも保護対象に加わるなど、制度が大きく変わろうとしています。本記事では、改正内容をわかりやすく解説し、企業のリスクや注意ポイントを整理します。
*以下の内容は本項作成時である令和7年6月末日現在における情報に基づく内容です。
公益通報者保護法とは
公益通報者保護法(以下、「法」といいます。)は、企業や行政機関における違法行為の是正を促進するため、内部通報制度の整備と通報者の保護を目的として制定されました。企業内の不正行為を通報したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁止するなど、労働者等の通報活動を保護する枠組みを提供しています。
近年、企業のコンプライアンス意識は高まりつつあるものの、通報者が組織内で不当な扱いを受ける事例や、内部通報制度が形骸化しているケースも少なくありません。そうした課題を踏まえ、改正法案が令和7年6月に参議院で可決・成立し、令和8年内には施行される予定です。
公益通報とは
公益通報とは、①法定の者(労働者、役員、1年以内に退職した者等)が、②不正の目的ではなく、③自身の役務提供先に対して、現在行われている、あるいはまさに生じようとしている事実に係り、④対象法令の罰則の対象となり得る規定に違反する行為を、⑤法定の通報先に⑥通報することを指します。
通報対象となる法律は、食品衛生法、労働基準法、労働安全衛生法、独占禁止法など多岐にわたり、広範な分野に及びます。企業としては、自社業務がどのような法令に関係しており、どのような行為が通報対象となり得るかを把握しておくことが重要でしょう。
法改正の概要

主な改正点は以下のとおりです。
これらの改正は、企業にとってコンプライアンス体制全体の見直しが求められるものであり、特に人事・労務の観点からも慎重な対応が求められます。
改正法による変化
今回の改正では、通報体制が実際に機能しているか、事業者には形式的な整備だけでなく、実効性のある対応体制の構築が求められるようになります。これにより、企業の実務にはどのような影響があるのか、主な変更点を以下で解説します。
(1)事業者が公益通報に対し適切な対応をする体制整備の実効化
前回令和2年の改正により、従業員300人超の事業者に対して内部通報体制の整備が義務化されましたが、今回の令和7年改正では、その実効性を担保するため、消費者庁による立入検査や是正命令の制度化が盛り込まれました(法15条の2第2項、16条1項)。
企業が通報対応体制を適切に整備していない場合には、指導・助言や勧告がなされ、それにも従わない場合には是正命令が発出され、さらにこれにも従わなければ、罰則(30万円以下の罰金)も科されることがあります(法15条、15条の2、21条2項1号)。
なお、報告や立入検査に対し虚偽の報告をしたり、検査を拒否したりした場合には、30万円以下の罰金(従業員300人以下の企業については、20万円以下の過料)が科される可能性があります(法21条2項2号)。
(2)公益通報者の範囲の拡大
これまで保護対象となっていたのは、「労働者」「退職後1年以内の者」等でしたが、今回の令和7年改正により、フリーランスも新たに保護対象となりました(法2条1項3号)。
フリーランスとは、「特定受託事業者」(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律2条)を指し、①「個人であって、従業員を使用しないもの」、または②「法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者)がなく、かつ、従業員を使用しないもの」のいずれかに該当する者です。
なお、この①②における「従業員」とは、週20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者を指しますので、委託先に従業員がいる場合でも、直ちにフリーランスに当たらないとは限らない点に注意が必要です。
これにより、外注先の者が通報を行う可能性が高まり、従前以上に幅広い関係者に対する制度周知とリスク管理が求められます。
(3)公益通報を抑制する行為の禁止
事業者が、労働者等に対し、正当な理由なく公益通報をしない旨の合意を求めること等により、公益通報を妨げる行為をすることが禁止され、これに違反してされた合意は無効となります(法11条の2)。
また、事業者が正当な理由なく、公益通報者を特定することを目的とする行為も禁止されます(法11条の3)。
(4)公益通報による不利益取扱いの禁止
従前から不利益取扱いは禁止されていましたが、今回の改正ではその実効性を高めるため、通報後1年以内(事業者が通報を知って不利益取扱いをした場合には、通報を知った日から1年以内)に行われた解雇・懲戒処分等について、「通報を理由とするものと推定」されるとの規定が新設されました(法3条3項)。
通常、裁判においては、解雇・懲戒処分の無効を労働者が主張・立証しなければなりませんが、上記の場合には、会社が通報を理由とするものではないことを主張・立証しなければなりません。
さらに、通報者への不利益取扱いを行った場合、個人には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人には最大3,000万円の罰金が科される可能性があります(法21条1項)。これは実務上、企業の人事処分等が重大な法的リスクを伴うことを意味します。
懲戒、異動などの判断については、公益通報との関連性があると疑われないよう、根拠を文書化して用意しておくことが対策として挙げられます。もっとも、通報から1年間、または通報を知ってから1年間は、労働者等への不利益な取扱いについては慎重になるべきでしょう。
おわりに

令和7年6月の法改正は、公益通報者の保護を制度的に強化し、企業に対する規律と責任を一層重くする内容となっています。特に、公益通報に対して事業者が不適切な対応をすれば、実効的な不利益を受けるように改正されたため、適切な対応を促す改正だったといえるでしょう。
労務管理の観点では、就業規則の見直し、人事・評価制度との整合、処分の妥当性確保、さらには通報対応者の確保や管理職への研修を行うことにより、紛争を事前に減らすことができるでしょう。
労働者が、外部に会社に不利益な事実を述べたが、それが公益通報に当たるか分からない、または公益通報であったとしてどのような問題が発生するか分からないという場合には、弁護士に相談することをお勧めします。