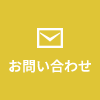変形労働時間制を導入した場合の残業代
当社では、仕事が月末に集中しており、月末は仕事量が増える一方で、月の半ば頃は仕事量が少なくなります。そのため、月末には時間外手当もかさむのですが、変形労働時間制を利用すれば、労働時間の配分を調整できると聞きました。変形労働時間制とは、どのような制度でしょうか。
変形労働時間制とは、労働基準法が定める1日8時間・1週40時間という労働時間の規制の適用を外し、ある一定期間を平均した所定労働時間が週法定時間(40時間)の枠内に収まっていれば良いという枠組みを認める制度です。
この制度により、使用者は、業務の繁閑がある場合、忙しい時期には1日10時間の所定労働時間にしたり、1週45時間の所定労働時間にしたりする一方で、忙しくない時期には1日または1週の所定労働時間を減らして、全体を平均して週40時間以内の所定労働時間とすることができます。1日8時間・1週40時間を超える所定労働時間を設定した期間については、設定された所定労働時間を超えない限り、残業代を支払う必要がなくなりますので、使用者にとっては、残業代の支払いを抑えつつ、業務の繁閑に応じて労働時間を変化させることができるというメリットがあります。
変形労働時間制には、現在、①1カ月単位の変形制、②1年単位の変形制、③1週間単位の非定型的変形制の3種類があります(このほか、似たような制度としてフレックスタイム制があります)。本件のように1か月単位で業務の繁閑が生じる場合には、①1カ月単位の変形性の導入が考えられるでしょう。
なお、対象期間の長短により、弾力化の程度や労働者に与える影響も異なってきますので、各制度には、それぞれ異なる要件が設けられています。例えば、1か月単位の変形制の場合は、就業規則によっても導入が可能ですが、それ以外の場合には労使協定の締結が必要であり、1年単位の変形制では所定労働時間の上限も設けられています。
このような変形労働時間制は、労働者にとっては、忙しい時期の労働時間が長くなり、これまで支払われていた残業代が少なくなりますので、内容や運用次第では、労働者の健康や生活に大きな影響が生じるおそれがあります。
そのため、要件は厳格に捉えられており、法で定められた要件を一つでも満たしていなければ、変形労働時間制は無効となり、労働基準法に従った労働時間規制や残業代の支払義務が課されることになります(変形労働時間制が無効とされた裁判例は、数多く出ています)。
導入に当たっては、慎重な制度設計を行うとともに、労使間において協議を尽くしていく必要があるでしょう。
変形労働時間制を導入した場合、どのような場合に残業代の支払いが必要になるのでしょうか。
変形労働時間制のもとでは、ある一定期間を平均した所定労働時間が週法定時間(40時間)の枠内に収まっていれば、1日8時間や1週40時間を超える労働も、直ちに時間外労働とはなりません。
もっとも、時間外労働が一切生じないわけではありません。
まず、①1日8時間・1週40時間を超えた所定労働時間が定められている週や日(繁忙期)については、その所定時間を超える労働は時間外労働となります。 次に、②1日8時間・1週40時間の範囲内で所定労働時間が定められている週や日(閑散期)については、1日8時間・1週40時間を超える労働が時間外労働となります。
さらに、変形期間を通じた総労働時間が、同期間の法定労働時間の総枠を超える場合についても、総枠を超える(上記①②で時間外労働とされた時間は除く)労働が時間外労働となります。
このように、変形労働時間制を導入した場合であっても、労働時間を適切に管理して時間外労働時間を把握し、法に基づいて算定した割増賃金(残業代)を支払うことが必要となります。
なお、変形労働時間制を導入した場合であっても、深夜労働や休憩・休日に関する規制は適用されますので、深夜労働や休日労働に対する割増賃金については、原則通り支払う必要があります。